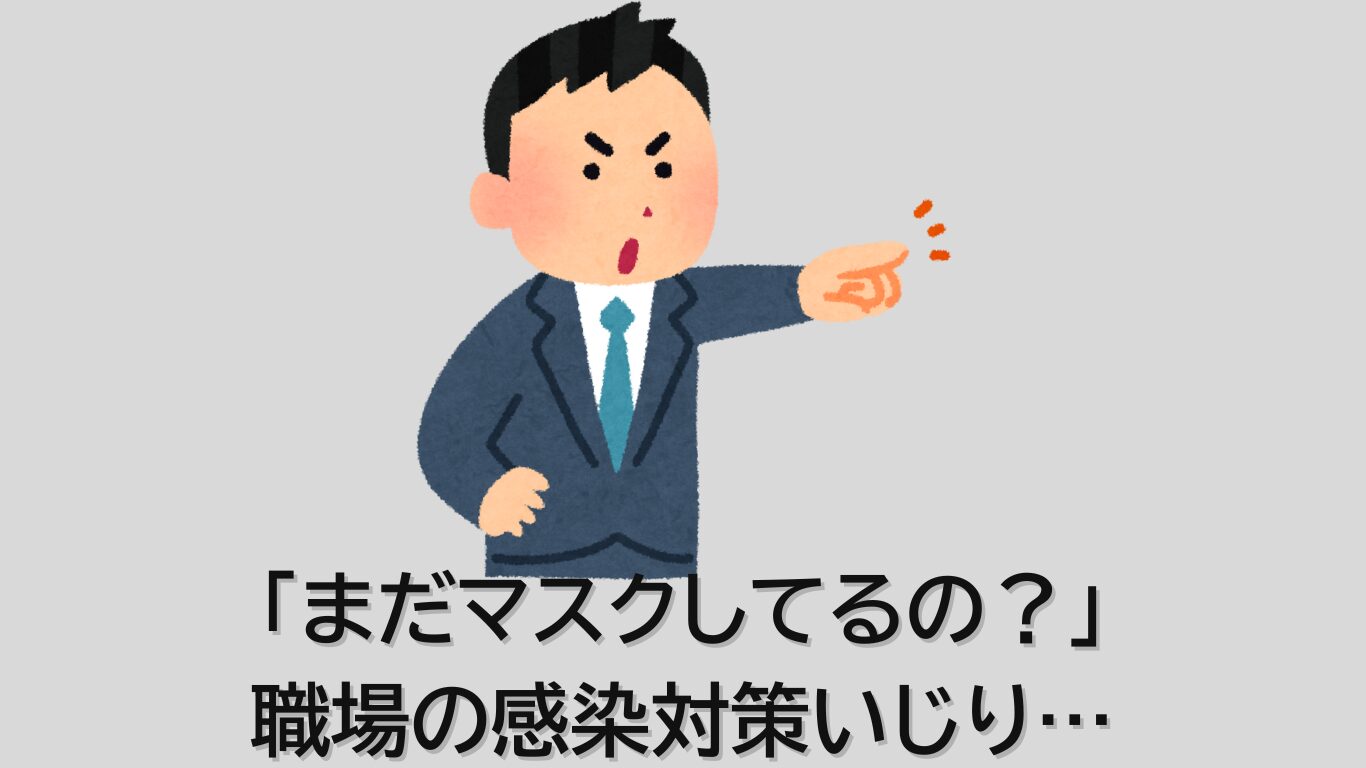「今どきまだマスクしてる人って、空気読めないよね〜」
マスクを着けて出社しただけなのに、同僚からこんな風に言われてモヤッとした経験はありませんか?
「マスク外して話してよ」
「もう終わったでしょ?神経質すぎる」
「会食断るなんて、付き合い悪いね」
私も実際に、家族に高齢者がいるためマスクを継続着用していたところ、毎日のように「まだしてるの?」と言われ続けました。
最初は笑って済ませていましたが、毎日続くとさすがにストレスが蓄積していきました。
コロナ禍を経験した今でも、感染対策をめぐる嫌がらせは職場で日常的に起きています。
「もう普通に戻ろうよ」という空気の中で、自分なりの健康管理を続けるのは本当に大変ですよね。
この記事では、そんな「コロナハラスメント(コロハラ)」の実態と、個人の健康管理方針を守るための具体的な対処法を、実体験をもとにお伝えします。
【参考記事】【完全版】職場の〇〇ハラスメント20選|種類・事例・対処法まとめ
なぜ職場で感染対策がこんなに批判されるのか?
「正常化」への強い欲求
私が人事相談を受けていた時期に気づいた、コロハラが生まれる心理的背景:
「もう普通に戻りたい」という切実な願望
3年間のコロナ禍で疲弊した人々の「早く元の生活に戻りたい」という気持ちは理解できます。
でも、その願望が強すぎて、まだ対策を続ける人を「足を引っ張る存在」として見てしまうのです。
自分の選択の正当化
マスクを外した人が、マスクを続ける人を見ると「自分の判断は正しかったのか?」という不安を感じます。
その不安を解消するために、異なる選択をする人を批判してしまうのです。
私の上司も「俺はもうマスクしないって決めたんだ。みんなもそうすべきだ」と強く主張していました。
これは自分の決断への確信を得たい心理の表れでした。
集団同調圧力の復活
「みんなで同じ方向に」という集団心理
日本特有の同調圧力が、感染対策でも強く働きました。
「みんながマスクを外しているのに、あの人だけ着けている」という状況への違和感です。
異なる選択への不寛容
私の職場でも「マスク派」と「ノーマスク派」という対立構図が生まれました。
お互いが相手の選択を批判し合う不毛な争いが続きました。
職場環境への深刻な影響
コロハラが蔓延すると起きる問題:
健康管理への萎縮効果
感染対策を続けたい人が、周囲の目を気にして対策をやめてしまう。
結果として、本当にリスクの高い人(基礎疾患がある人、高齢家族と同居している人)が適切な対策を取れなくなります。
職場での心理的安全性の破綻
「自分だけ違う選択をしたら批判される」という恐怖から、本音を言えない職場環境になってしまいました。
これは感染対策以外の件でも、多様性を認めない文化につながりました。
不必要な対立と分断
本来は個人の判断に委ねられるべき事項で、職場が二分されてしまいました。
これは業務効率にも悪影響を与えました。
職場での感染対策への批判がハラスメントになるケース
個人の健康管理への干渉行為
私が実際に見聞きした、明らかに問題のあるコロハラの事例:
感染対策への批判・強要
- 「まだマスクしてるの?時代遅れ」という嘲笑
- マスクを外すよう直接的に要求する
- 感染対策を「過剰反応」「神経質」と人格攻撃
- 「空気が読めない」「チームワークがない」という決めつけ
健康状態への過度な詮索
- 体調不良時の「コロナ?」というしつこい質問
- 検査結果や医師の診断の詳細な報告を要求
- 家族の健康状態まで詮索する
- 過去の感染歴について根掘り葉掘り聞く
行動制限・差別的取扱い
- 感染対策をする人の会議参加を敬遠
- 「過度な対策」を理由とした業務からの排除
- マスク着用者を別席に座らせる隔離行為
- 会食や懇親会から事実上の排除
法的・倫理的に問題となる根拠
労働安全衛生法の観点
企業には従業員の健康と安全を確保する義務があります。
個人の健康管理選択を妨害することは、この義務に反します。
個人の自由権の侵害
健康管理は個人の基本的権利です。
それを制限したり批判したりすることは、人権侵害にあたります。
パワーハラスメント
上司が部下に感染対策をやめるよう圧力をかけたり、対策を続ける人を嘲笑したりすることは、優越的地位を背景とした嫌がらせとして問題視されます。
私が実際に試した対処法とその効果測定
個人方針の明確化と一貫性
自分なりの基準の設定
私が作成した「個人感染対策方針」:
【個人の健康管理方針】
1. 家族に高齢者がいるため、リスク軽減を優先
2. 医学的根拠に基づいた判断を継続
3. 他者の選択は尊重するが、自分の選択も尊重を求める
4. 状況に応じて柔軟に見直しを行う
効果:★★★★☆
明確な基準があることで、批判された時に感情的にならずに説明できました。
「なんとなく」ではなく「理由がある」ことを示せたのが効果的でした。
法的根拠を示した対応
健康管理の権利を主張
しつこい批判に対しては、以下のように対応しました:
「感染対策については、個人の健康管理の一環として医学的根拠に基づいて判断しています。他の方の選択は尊重しますので、私の選択についても尊重していただけるようお願いします」
効果:★★★★★
「個人の権利」として主張することで、相手も反論しにくくなりました。
特に「他者の選択も尊重する」と付け加えることで、一方的ではない姿勢を示せました。
職場環境の改善提案
人事部への多様性尊重の提案
私が人事部に提出した改善案:
- 健康管理の多様性を認める方針の策定
- コロハラ防止研修の実施
- 相談窓口での健康管理嫌がらせの受付
- 柔軟な働き方の推進(リモート参加の活用など)
効果:★★★☆☆
すぐに制度化されたわけではありませんが、問題意識を共有してもらえました。
同じような相談が他からも寄せられていたことがわかり、個人的な問題ではないことが明確になりました。
理解者との連携
同じ価値観を持つ同僚とのネットワーク
職場で感染対策を続けている人5人で情報交換グループを作りました。
活動内容:
- お互いの体験談の共有
- 効果的な対応方法の検討
- 精神的な支え合い
- 正しい医学情報の共有
効果:★★★★☆
「自分だけではない」と感じることで、精神的な支えになりました。
また、集団で対応することで、個人攻撃されるリスクも軽減されました。
意外だった気づき:対立から共存への道
この問題で悩んでいる時、感染対策について異なる考えを持つ同僚と深く話し合う機会がありました。
その時の発見:
お互いの事情を知らなかっただけ
マスク反対派の同僚:「実は、マスクで肌荒れがひどくて皮膚科通いをしている。でも、それを理由にするのは甘えだと思われそうで言えなかった」
マスク継続派の私:「父が糖尿病で、感染したら重症化リスクが高い。でも、家族の事情を職場で詳しく説明するのも…」
共通点は「相手に迷惑をかけたくない」
結局、どちら側も「周りに迷惑をかけたくない」という気持ちは同じでした。
対立していたのは手段であって、目的ではなかったのです。
この気づきから、私たちのグループは「対策の違いを認め合う職場作り」を目指すようになりました。
コロハラから身を守る実践的コミュニケーション
批判を受けた時の対応テクニック
感情的にならない返答方法
批判された時の効果的な切り返し:
相手:「まだマスクしてるの?もう大丈夫だよ」
自分:「ありがとうございます。私なりに状況を判断して決めています」
相手:「神経質すぎない?」
自分:「人それぞれリスクの感じ方が違いますからね。○○さんの選択も理解できます」
ポイント:
- 相手の選択も認める姿勢を示す
- 感情論ではなく判断基準があることを伝える
- 長い説明はせず、簡潔に済ませる
予防的コミュニケーション
事前に方針を伝えておく
新しいチームに参加する時など、事前に自分の方針を伝えておくことで、後々の摩擦を防げます:
「感染対策については、家族の状況も考慮して個人的に判断しています。他の方の方針は尊重しますので、私の判断についてもご理解いただけると助かります」
まとめ:健康管理は個人の基本的権利
「もうコロナは終わった」という空気の中でも、個人のリスク評価や健康管理方針は人それぞれです。
あなたの感染対策への選択は、誰かに批判される筋合いのものではありません。
今すぐできること:
- 自分なりの健康管理基準を明確にしておく
- 批判された時は「個人の判断」として毅然と対応する
- 相手の選択も尊重する姿勢を示すことで対立を避ける
私の経験では、コロハラの多くは「相互理解の不足」が原因でした。
お互いの事情や考えを理解し合えれば、多くの場合は共存できます。
大切なのは、感染対策の選択で職場が分断されることではなく、多様な価値観を認め合いながら協力していくことです。
あなたには自分と家族の健康を守る権利があります。
周囲の圧力に負けることなく、あなた自身の判断を大切にしてください。
そして、異なる選択をする人への理解も忘れずに、お互いを尊重し合える職場環境を一緒に作っていきましょう。
関連記事
個人の健康管理・自己決定権
- 職場で個人の価値観を尊重してもらうためのコミュニケーション術
- 健康に関する自己決定権を職場で守る方法
職場の同調圧力・ハラスメント対策
- 職場の同調圧力に負けない心理的な準備と対処法
- 価値観の違いを理由とした職場いじめへの対策